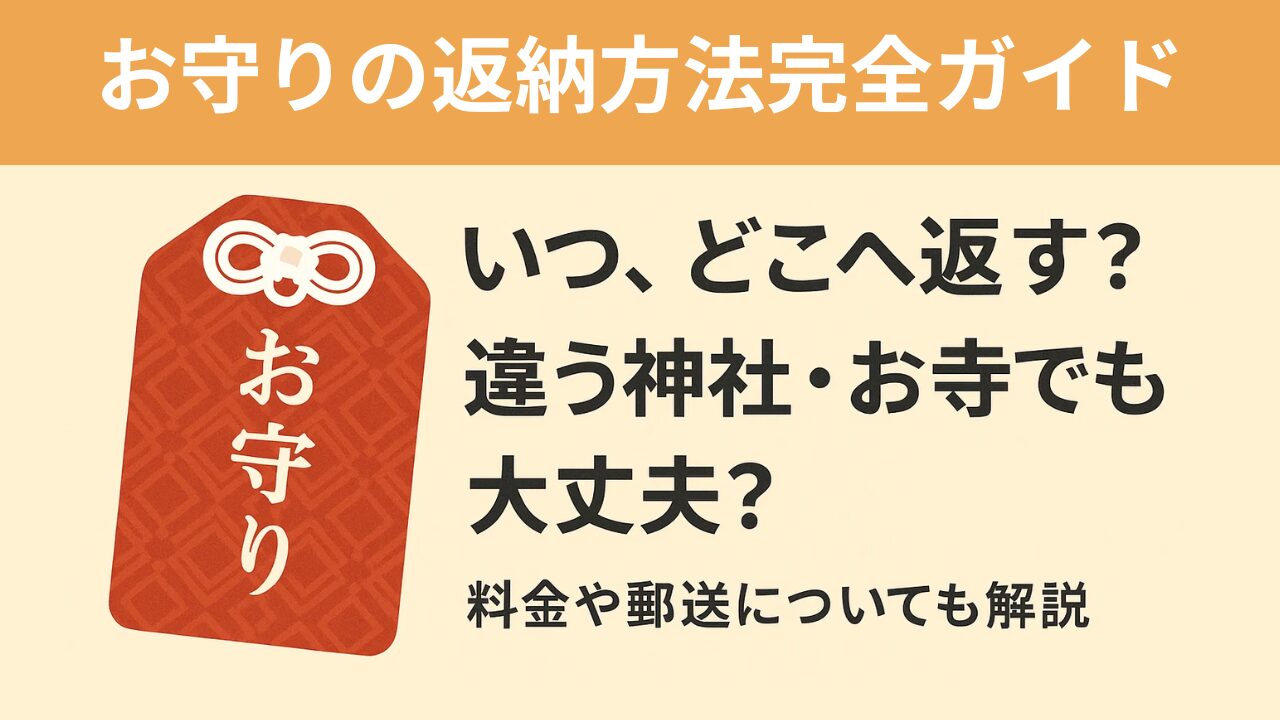大切にしているお守り、授かってから一年が経ち、どう返納すれば良いか迷っていませんか?
「授かった神社が遠方でなかなか行けない」
「違う神社やお寺でも返してもいいのだろうか」
「料金はかかるの?」など、
お守りの返納には様々な疑問がつきものです。
この記事では、一年間あなたを見守ってくれたお守りへの感謝を伝え、正しく手放すための方法を徹底的に解説します。この記事を最後まで読めば、返納の時期や場所、費用に関するあらゆる疑問が解消され、清々しい気持ちで新たなご縁を結ぶ準備が整うでしょう。

そもそも、お守りはなぜ返納するの?
お守りを授かることはあっても、返納についてはあまり意識したことがない、という方も多いのではないでしょうか。まずはじめに、なぜお守りを返納する必要があるのか、その意味と理由について理解を深めましょう。
お守りの返納は、決して不敬な行為ではありません。むしろ、神様や仏様に対する感謝の気持ちを表す、非常に丁寧で大切な行為なのです。
お守りの効力は一般的に「1年」
お守りには、神様や仏様の御霊(みたま)の力が込められており、私たちを災厄から守り、願いが成就するよう後押ししてくださいます。しかし、その効力は永遠に続くわけではなく、一般的には「1年」が目安とされています。
時間が経つにつれて、お守り自身が持ち主の身代わりとなって災厄や穢れ(けがれ)を吸い取ってくれるため、その力は徐々に弱まっていくと考えられています。そのため、一年という節目で古いお守りを神社やお寺にお返しし、新しいお守りを授かることで、再び新たな神様・仏様の力をいただき、次の一年を健やかに過ごすことができるのです。これは、日本の年中行事や「常若(とこわか)」という、常に若々しく瑞々しい状態を尊ぶ神道の思想にも通じています。
返納は「感謝」を伝えるための大切な儀式
お守りを返納する最も大きな意味は、「感謝を伝えること」にあります。一年間、無事に過ごせたことへの感謝、願いが叶ったことへの御礼を込めて、神様・仏様のもとへお返しするのです。
単に「古いものを処分する」という考え方ではなく、「一年間お守りいただき、ありがとうございました」という真心を込めて返納することで、礼を尽くし、次のご縁へと繋がっていくのです。役目を終えたお守りを丁重にお返しすることは、神様・仏様との良好な関係を維持するための、大切なコミュニケーションと言えるでしょう。

お守りを返納する時期はいつが最適?
お守りを返納する大切さがわかったところで、次に気になるのが「いつ返納すれば良いのか」というタイミングです。基本的には一年が目安ですが、その他にも適切な時期がいくつかあります。
基本は願い事や状況に合わせて
お守りを返納する最適な時期は、授かったお守りの種類や、ご自身の状況によって異なります。
授与から1年が経過したタイミング
最も一般的で基本となるのが、お守りを授かってから1年が経過したタイミングです。特に年末から年始にかけては、多くの神社仏閣で古いお守りを返納するための「古神札納所(こしんさつおさめしょ)」が設けられるため、返納しやすい時期と言えます。初詣の際に、前年のお守りを返納し、新しい年のお守りを授かるという流れが、日本の美しい慣習として根付いています。
願いが叶った時
安産祈願や合格祈願、病気平癒など、特定のお願いごとがお守りに込められている場合は、その願いが成就した時が返納の絶好のタイミングです。願いが叶った際は、お守りを返すだけでなく、必ず「御礼参り」を行いましょう。神様・仏様に願いが聞き届けられたことへの感謝を直接お伝えすることで、より深いご縁を結ぶことができます。
1年を過ぎてしまっても問題ありません
「気づいたら1年以上経ってしまっていた…」と焦る必要は全くありません。お守りの返納に厳格な期限が設けられているわけではなく、1年というのはあくまで目安です。大切なのは、感謝の気持ちを忘れないこと。たとえ数年が経過していても、返納したいと思った時がそのタイミングです。神様・仏様は、私たちの真心をいつでも受け入れてくださいます。手元にあることに気づいたら、なるべく早めに神社やお寺へお返ししましょう。
お守りの返納場所はどこ?基本的な方法を解説
返納の時期がわかったら、次は具体的な返納場所と方法です。どこへ、どのようにしてお返しすれば良いのでしょうか。最も丁寧な方法から順に見ていきましょう。

原則は「授かった神社やお寺」へ
お守りを返納する際の最も丁寧で正式な方法は、そのお守りを授かった(購入した)神社やお寺へ直接お返しすることです。自分自身の願いを見守ってくれた神様・仏様へ直接「ありがとうございました」と御礼を伝えることができます。
境内には、「古神札納所(こしんさつおさめしょ)」や「納札殿(のうさつでん)」、「お札お納め所」などと書かれた場所が設けられています。名称は神社仏閣によって異なりますが、古いお札やお守りを納めるための専用の箱や建物です。そちらへ静かにお守りを納めましょう。もし場所がわからない場合は、社務所や寺務所で尋ねれば親切に教えてもらえます。
返納の際は、ただお守りを箱に入れるだけでなく、本殿や本堂で手を合わせ、一年間の感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。
どんど焼きでお焚き上げしてもらう
地域によっては、「どんど焼き」や「左義長(さぎちょう)」と呼ばれる火祭りの神事で、お守りをお焚き上げしてもらう方法もあります。これは主に小正月(1月15日前後)に行われる行事で、お正月のしめ縄や門松、書初めなどと一緒に、古いお守りやお札を燃やして、炎と共に神様を天にお送りするという意味合いがあります。
ご自身の地域でどんど焼きが行われているか、また、お守りの持ち込みが可能かどうかは、事前に自治体や地域の神社にご確認ください。勢いよく燃え上がる炎には、穢れを祓い清める力があるとされています。
【悩み解決】違う神社やお寺でも返納できる?
多くの人が抱える最大の疑問が、「授かった場所とは違う神社やお寺に返納しても良いのか?」という点です。遠方に引っ越してしまった、旅行先で授かったなど、様々な事情で元の場所へ行けないケースは少なくありません。
結論から言うと、状況に応じて「可能」な場合と「避けるべき」場合があります。ここではその違いを詳しく解説します。
違う神社への返納は「条件付きで可能」
授かった神社とは別の神社へお守りを返納することは、基本的には可能です。多くの神社では、他の神社のお守りであっても、古神札納所で受け入れています。神道には「八百万の神」という考え方があり、多くの神様は繋がっているとされているため、比較的寛容に対応してくれる場合が多いです。
ただし、より丁寧に対応したい場合は、同じ系統の神社に返納することをおすすめします。例えば、天満宮で授かった合格祈願のお守りは別の天満宮へ、八幡宮で授かった厄除けのお守りは別の八幡宮へ、といった形です。祀られている神様(御祭神)が同じであるため、より自然な形で感謝を伝えることができます。
とはいえ、近所に同じ系統の神社がない場合も多いでしょう。その際は、特にこだわらず最寄りの神社の古神札納所へお納めしても、一般的には問題ないとされています。
出典情報について
この見解は、神社本庁のウェブサイトや、多くの神社の公式サイト等で示されている一般的な考え方に基づいています。ただし、神社によっては独自の考えがある場合もございますので、ご心配な場合は事前に電話などで確認するとより安心です。
違うお寺への返納は「注意が必要」
お寺のお守りを違うお寺へ返納する場合は、神社よりも注意が必要です。仏教には、天台宗、真言宗、浄土宗、禅宗など、様々な宗派が存在します。そして、宗派が異なると、お祀りしている本尊や教義も異なるため、別のお寺のお守りを受け入れていないケースが少なくありません。
そのため、お寺のお守りは、原則として授かったお寺、もしくは同じ宗派のお寺へ返納するのがマナーです。ご自身の持っているお守りがどのお寺のものか、何宗のお寺なのかを確認し、同じ宗派のお寺が近くにあれば、そちらへ相談してみましょう。もし宗派がわからない、近くに同じ宗派のお寺がないという場合は、事前に電話で受け入れてもらえるか確認することをおすすめします。
【絶対NG】神社のお守りをお寺へ、お寺のお守りを神社へ
これは最も避けるべきケースです。神社のお守りをお寺へ、逆にお寺のお守りを神社へ返納することは、マナー違反とされています。
神社は「神道」、お寺は「仏教」という異なる宗教施設です。それぞれの教義や作法は全く異なります。例えるなら、全く別の会社に退職の挨拶に行くようなものです。お互いの領域を尊重し、必ず神社のお守りは神社へ、お寺のお守りは仏閣へお返しするようにしてください。
遠方で返納に行けない場合は?郵送での返納方法
「授かった神社やお寺が遠方でどうしても行けない」「体調が優れず外出が難しい」といった場合は、郵送で返納を受け付けてくれる神社仏閣もあります。ただし、すべての場所で対応しているわけではないため、事前の確認が必須です。

郵送対応の可否を必ず事前に確認
まず最初に、返納したい神社やお寺の公式ウェブサイトを確認するか、直接電話で問い合わせて、郵送での返納を受け付けているかを確認しましょう。「古札郵送受付」「お焚き上げ申込み」などの案内があれば、それに従います。無断で送りつけるのは絶対にやめましょう。
郵送で返納する際の基本的な手順
郵送での返納許可が取れたら、以下の手順で準備を進めます。
- お守りを白い紙で包む お守りをそのまま封筒に入れるのではなく、感謝を込めて綺麗な白い半紙や和紙、なければ白いコピー用紙などで丁寧に包みます。
- お焚き上げ料(初穂料・お布施)を同封する 郵送の場合は、お焚き上げをしていただく手間に対する謝礼として、お焚き上げ料を同封するのがマナーです。金額は神社仏閣によって指定されている場合もありますが、一般的にはお守りを授かった時と同額程度〜3,000円程度を志として納める方が多いようです。
- 現金書留で送る 現金を普通郵便で送ることは郵便法で禁止されています。 必ず郵便局の窓口で「現金書留」の封筒を購入し、その封筒にお守りとお焚き上げ料を入れて送ってください。
- 感謝の手紙を添える(任意) 必須ではありませんが、簡単なものでも構いませんので、一年間お守りいただいたことへの感謝の気持ちを綴った手紙を添えると、より心が伝わり丁寧な印象になります。
- 宛名を確認する 宛名は「〇〇神社 御中」または「〇〇寺院 御中」とします。部署名(社務所など)が指定されている場合は、それに従ってください。
お守り返納の料金はかかる?費用相場を解説
お守りを返納する際、費用がどのくらいかかるのかも気になるところです。結論から言うと、明確な「料金」が設定されているわけではありませんが、感謝の気持ちを表すのが一般的です。
基本的には「お気持ち」で
神社やお寺の古神札納所へ直接返納する場合、返納そのものに「料金」は発生しません。無料で納めることができます。
しかし、前述の通り、返納は感謝を伝える行為です。そのため、お守りを納めた後、本殿・本堂の前でお賽銭を入れるのが丁寧な作法とされています。お賽銭の金額に決まりはありません。5円(ご縁がありますように)や10円でも、感謝の気持ちがこもっていれば問題ありません。もちろん、お守りを授かった時と同程度の金額をお賽銭として納める方もいます。大切なのは金額ではなく、感謝の心です。
初穂料・お焚き上げ料の目安
郵送で返納する場合や、祈祷とあわせてお焚き上げをお願いする場合は、「お焚き上げ料」として費用がかかることがあります。神社では「初穂料(はつほりょう)」、お寺では「お布施」という名目になります。
金額の目安は、神社仏閣から指定がなければ、お守りを授かった時と同額程度と考えると良いでしょう。一般的には1,000円〜3,000円程度を納める方が多いようです。現金書留で送る場合は、この金額を同封します。
どうしても返納できない場合の最終手段(自宅での処分)
基本的には神社仏閣へお返しするのが大原則ですが、「海外在住で日本の神社仏閣が近くにない」「様々な事情でどうしても返納が不可能」という場合もあるかもしれません。その際の、あくまで最終手段としての自宅での処分方法について解説します。この方法は、神様・仏様への敬意を最大限に払った上で行うようにしてください。
自宅でのお清めと処分の手順
- 白い綺麗な紙を用意する 半紙や和紙が理想ですが、なければ白いコピー用紙などを用意し、その上にお守りを置きます。
- 塩でお清めをする お守りの上に、お清めの意味を持つ塩(できれば天然塩)をひとつまみ振りかけます。
- 手を合わせ、感謝を伝える お守りに向かって静かに手を合わせ、「一年間お守りいただき、ありがとうございました」と心の中で感謝の言葉を伝えます。
- 白い紙に包んで処分する 感謝を伝えた後、お守りをそのまま白い紙で丁寧に包みます。そして、他のゴミとは別の袋に入れ、自治体のルールに従ってゴミの日に出します。
この方法はあくまで緊急避難的な対処法です。お守りは神聖なものですので、ゴミとしてぞんざいに扱うのではなく、最後まで感謝と敬意の気持ちを持って手放すことが何よりも大切です。お守りの素材(木、布、金属、プラスチックなど)によって分別方法が異なるため、お住まいの自治体のルールを必ず確認してください。
まとめ:感謝の気持ちを込めて、お守りを正しく返納しよう
今回は、お守りの正しい返納方法について、時期や場所、費用、そして様々な疑問にお答えする形で詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 返納の意味:1年間見守ってくれたことへの「感謝」を伝える大切な行為。
- 返納の時期:授与から1年後、または願いが叶った時が目安。過ぎてしまっても問題ない。
- 返納の場所:授かった神社やお寺が基本。難しい場合は、他の神社(宗派が同じお寺)でも可能。
- 注意点:神社とお寺を間違えて返納するのはNG。
- 遠方の場合:郵送に対応しているか確認の上、現金書留で送る。
- 費用:基本は無料だが、感謝の気持ちとしてお賽銭や初穂料を納めるのが丁寧。
- 最終手段:自宅で処分する際は、塩で清め、感謝を伝えてから自治体のルールに従う。
お守りの返納は、決して義務や面倒な作業ではありません。
一年間の感謝を伝え、神様・仏様とのご縁を清々しく更新するための、前向きなステップです。この記事を参考に、あなたの大切なお守りを感謝の気持ちと共に正しく手放し、また新たな気持ちで素晴らしい一年をお迎えください。