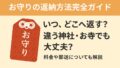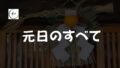日本の神社仏閣では、古くからの伝統に基づいた様々な行事が一年を通して執り行われています。このページでは、季節の移ろいとともに訪れる主な祭事やイベントを月ごとにまとめました。それぞれの行事には、人々の祈りや願いが込められています。
1月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 1月1日 | 元日(がんじつ) | 新年の始まり。多くの人が神社仏閣に初詣(はつもうで)に訪れ、一年の無病息災や平安を祈願します。 |
| 1月7日 | 人日の節句(じんじつのせっく) | 七草の節句とも呼ばれます。七草粥を食べて、無病息災と長寿を願います。 |
| 1月11日頃 | 鏡開き(かがみびらき) | 正月の間に神仏に供えた鏡餅を下ろし、お汁粉や雑煮にして食べることで、神仏からの力を授かるとされています。 |
| 1月15日 | 小正月(こしょうがつ) | 元日を中心とした「大正月(おおしょうがつ)」に対し、年の初めの満月の日を祝います。豊作を祈る行事や、どんど焼きなどが行われる地域も多くあります。 |
2月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
立春の前日
(2月3日頃) | 節分(せつぶん) | 季節の分かれ目であり、邪気を払うための行事が行われます。神社仏閣では豆まきが行われ、家庭では「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆をまきます。 |
2月最初の
午の日 | 初午(はつうま) | 全国の稲荷神社のご本社である、京都の伏見稲荷大社の祭神が稲荷山に鎮座した日とされ、全国の稲荷神社で盛大な祭礼が行われます。 |
3月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 3月3日 | 上巳の節句(じょうしのせっく) | 桃の節句やひな祭りとして知られ、女の子の健やかな成長と幸せを願います。 |
春分の日を
中心とした7日間 | 春彼岸(はるひがん) | 春分の日を中日(ちゅうにち)とした前後3日間、合計7日間のこと。先祖を供養するためにお墓参りをする仏教行事です。 |
4月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 4月8日 | 花まつり(はなまつり) | お釈迦様の誕生日を祝う仏教行事。灌仏会(かんぶつえ)とも呼ばれます。花御堂(はなみどう)に安置された誕生仏に甘茶をかけて祝います。 |
5月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 5月5日 | 端午の節句(たんごのせっく) | 男の子の健やかな成長と立身出世を願う行事。菖蒲(しょうぶ)を飾ったり、菖蒲湯に入ったりします。 |
6月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 6月30日 | 夏越の祓(なごしのはらえ) | 一年の前半の最終日に、半年間の罪や穢れ(けがれ)を祓い清める神事です。多くの神社で茅の輪(ちのわ)くぐりが行われ、残り半年の無病息災を祈ります。 |
7月・8月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 7月7日 | 七夕の節句(たなばたのせっく) | 星祭りとも呼ばれ、願い事を書いた短冊を笹に飾ります。 |
7月13日〜16日
または
8月13日〜16日 | お盆(おぼん) | 先祖の霊を迎えて供養する一連の仏教行事。地域によって時期が異なり、東京などでは7月、全国的には月遅れの8月に行われることが多いです。 |
9月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 9月9日 | 重陽の節句(ちょうようのせっく) | 菊の節句とも呼ばれ、菊の花を飾ったり、菊酒を飲んだりして長寿を願います。 |
秋分の日を
中心とした7日間 | 秋彼岸(あきひがん) | 秋分の日を中日とした前後3日間、合計7日間。春彼岸と同様に、先祖を供養するためにお墓参りが行われます。 |
11月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 11月の酉の日 | 酉の市(とりのいち) | 11月の暦で「酉」にあたる日に行われる祭り。主に鷲(おおとり)神社や大鳥神社で、開運招福や商売繁盛を願う縁起物の熊手が売られます。 |
| 11月15日 | 七五三(しちごさん) | 男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳になる年に、子供の成長を祝い、これからの健康を祈願して神社にお参りします。 |
| 11月23日 | 新嘗祭(にいなめさい) | その年に収穫された新しい穀物を神様にお供えし、収穫に感謝するお祭り。宮中祭祀のひとつですが、全国の神社でも行われます。 |
12月
| 日付 | イベント名 | 概要 |
|---|
| 12月31日 | 年越の祓(としこしのはらえ) | 大祓(おおはらえ)とも呼ばれます。一年の納めとして、知らず知らずのうちに犯した罪や穢れを祓い清め、清らかな心身で新年を迎えるための神事です。 |
| 12月31日 | 除夜(じょや) | 大晦日の夜のこと。多くの寺院で、人間の煩悩の数とされる108回除夜の鐘が撞かれ、古い年の煩悩を払い清めて新年を迎えます。 |